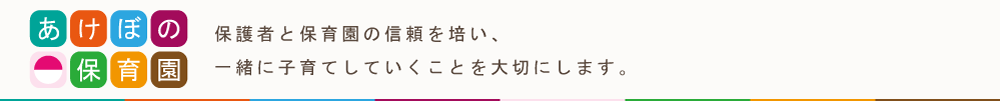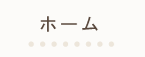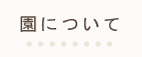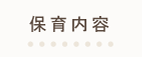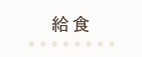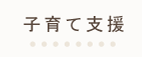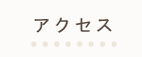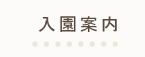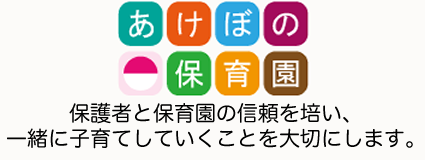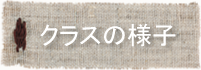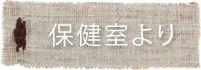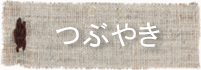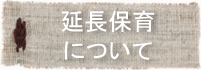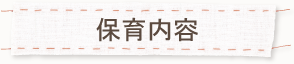
保健室より
2025年度1月
【 熱の出始め 】
人間の脳は設定温度を「だいたい37℃前後」に保っています。ウイルスが侵入してくると、免疫細胞が働き、いろんな警報物質を出します。これらが脳の血管などを介して、神経回路に作用し「ウイルスと闘うために、体温を上げろ」という指令が出ます。すると脳は「設定温度を39℃へアップ!」と決断します。設定温度を39℃にしたのに体温が37℃だと、脳は「寒い!設定より低い!」と判断します。これが熱の出始めに感じる「悪寒、寒気」の正体。だから脳は筋肉に「震えて熱をつくれ!」と命じます。つまり、熱の出始めは手足が冷たく震えるのです。この段階では、体は「温まりたいモード」なので、保温してあげましょう。
【 解熱期 】
ウイルスとの闘いが一段落し、脳が「もう高熱は不要」と判断すると、設定温度を37℃位に戻します。その時点で体温が39℃だと、「熱過ぎる状態」。そこで脳は「余分な熱を捨てろ!」と指令を出します。末梢血管を広げて熱を逃し、汗腺を開き汗を出す。こうして解熱するのです。
【 厚着して汗をかけば早く解熱する? 】
これは危険な考え!良かれと思った厚着が招く3つの問題は「うつ熱」「脱水の加速」「SIDSのリスクアップ」です。自分で「暑いから布団をはぐ」「服を脱ぐ」ことができれば良いのですが、乳児や、つらいとき等、できないことが多いです。すると、熱がこもり、40℃以上の高体温になります。熱が上がると呼気や皮膚から自然に失われる水分が増えます(不感蒸泄)。そんなときに厚着させるとサウナ状態になり、あっという間に脱水です。体の血液量は減り、ウイルスと闘うための血流も維持できず、回復に必要な体力まで奪ってしまいます。そして「SIDS」環境要因として「行き過ぎた厚着・高い室温」などによる暖め過ぎはリスク因子の一つなのです。
布団や毛布を掛け過ぎない・震えていれば少し掛ける
・熱くなってきたら薄くする
・こまめに水分補給
で、快適にしてあげましょう。
2025年度12月
乳幼児期は乾燥しやすい時期
乳幼児は皮膚を守る機能が弱く、病原菌やアレルゲンなどが侵入し、皮膚トラブルを起こしやすいです。トラブルを予防するためには、正しいスキンケアが重要になります。
正しいスキンケアの基本は、「きれいに洗って清潔にする」「しっとり保湿する」ことです。
【洗うときのポイント】
- 石けんはできるだけ成分は添加物の少ないものを選びましょう。
- そしてよく泡立てます。強くこすらず、泡で洗ってあげましょう。
- 脇の下や足の付け根、しわの多い部分は汚れが溜まりやすいです。 しわを伸ばして丁寧に洗ってあげましょう。
- 石鹸成分が残っているとかゆみの原因になります。よく流しましょう。
【保湿のポイント】
- 保湿をするタイミングは朝の登園前とお風呂のあとです。 お風呂あがり、身体を拭いたら早めに保湿をしましょう。
- 保湿剤は子ども用の低刺激なものを選ぶとよいでしょう。
- 保湿剤はたっぷりと、そしてやさしく塗ります。
- 保湿剤の量は、 1FTU(ワン・フィンガー・チップ・ユニット)といい、 手のひら2枚分の面積に塗る適量の目安です。

お子さんにスキンケアをしてあげることで、スキンシップが生まれます。
親子のスキンシップはお子さんの健やかな成長にもつながり、また触れあうことによりハッピーホルモンといわれる「オキシトシン※」がお互いに分泌されるそうです。
※オキシトシン
愛着を深め成長を促し、
情緒を安定させる効果があります。

2025年度11月
おなかの健康(うんち)について
11月は“いい(11)○○の日”が沢山あります。11月10日の“いいトイレ”の日にちなみ、うんちのお話をお届けします。排便後のうんちを観察することで身体の健康状態をチェックできます。お子さんにもうんちが出た後はどんなうんちがでたのか見ようねと声をかけて、家族みんなで健康管理をしてみてはいかがでしょうか。
コロコロうんち![]()
ウサギのフンのようにコロコロしている。においはとてもくさい…。水分や食物繊維が足りない。
バナナうんち![]()
力まずスルンっと出る。あんまり臭くない。身体も腸内環境もgood!
ヒョロヒョロうんち![]()
腸内環境が乱れかかっている。体調もあまりよくない時に出がち。出る量は少なく、くさい…。
ドロドロ・
ビシャビシャうんち![]()
泥状や水のようなうんち。いわゆる下痢。体調はもちろん悪い。くさい。酸っぱい臭いがすることもある。
こどもも大人もバナナうんちが出るように生活習慣を整えよう!
朝ごはんをたべよう
朝食を食べることで胃腸が刺激されて自然な便意がもよおされることが期待できます。
朝ごはんは元気な一日を過ごすための大切なエネルギー源でもあります。
朝ごはんの後はトイレへGO
食後に便意を感じたら我慢せずに行きましょう。時間がないからといって我慢して後回しにすると便秘につながる可能性があります。
朝は余裕をもってトイレの時間を確保できるといいですね
食物繊維の多い食品を意識して
食物繊維には腸内環境を整える働きがあります。野菜・キノコ・豆・発酵食品の納豆やヨーグルトに多く含まれています。水分補給も忘れずに
身体を動かそう
身体を動かすことで腸も動きます。大人も激しい運動だけではなく、日常的に続けられる散歩やウォーキングもおすすめです。
過去のお知らせはこちら >>